「糖質制限ダイエット」という言葉をよく耳にしますが、糖質を極端にカットするとどんなリスクがあるかご存じでしょうか?
健康や美容のために糖質を意識するのは大切ですが、全く取らないのは逆効果になることもあります。今回は、糖質の役割と不足によるリスク、さらに1日に必要な糖質量や食事の目安についてわかりやすく解説します。
⸻
糖質の役割とは?
糖質は三大栄養素(たんぱく質・脂質・糖質)のひとつで、特に「エネルギー源」として重要な役割を果たします。脳や赤血球は基本的にブドウ糖しか使えないため、糖質が不足するとすぐに体調や思考力に影響が出ます。
また、筋肉や肝臓にはグリコーゲンとして糖が蓄えられ、運動時や空腹時にエネルギーを補います。つまり、糖質は私たちが活動するための「燃料タンク」とも言える存在です。
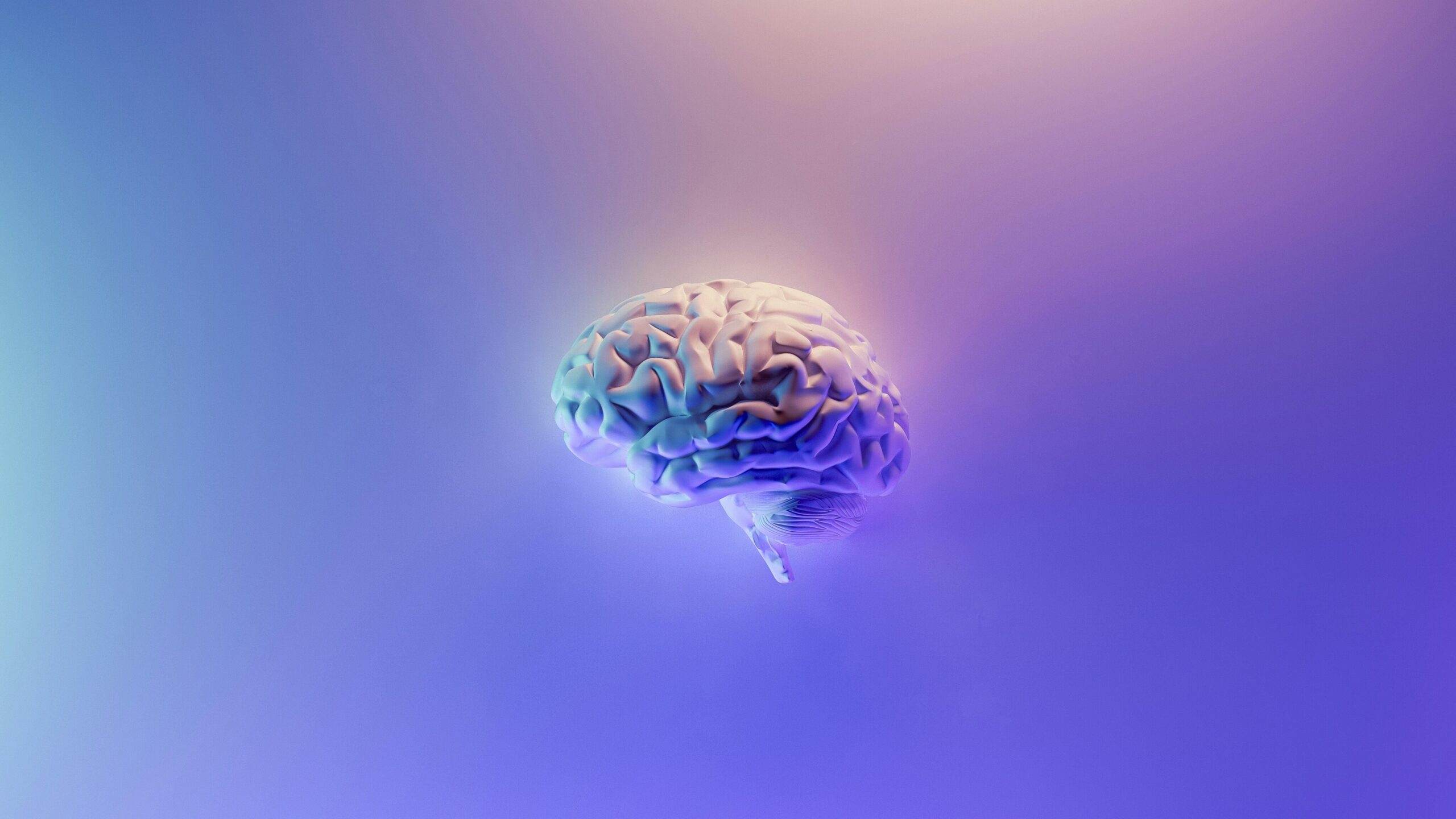
⸻
糖質を全く取らないと起こるリスク
糖質をゼロに近いレベルまで制限すると、次のようなリスクが考えられます。
1. エネルギー不足による疲労感
体がだるい、力が出ないと感じやすくなります。
2. 集中力や記憶力の低下
脳の主要なエネルギーはブドウ糖。糖質不足は思考力の鈍化や注意力散漫を招きます。
3. 筋肉量の減少
糖質が足りないと、体は筋肉を分解してエネルギーを作ろうとするため、基礎代謝が落ちやすくなります。
4. 便秘や体調不良
糖質を含む穀物や果物を避けると、食物繊維やビタミン類の摂取も不足しがちに。結果的に腸内環境が悪化することもあります。
⸻
脳や認知症への影響
特に注目したいのが「脳」への影響です。脳は体重の2%程度しかありませんが、エネルギー消費量は全体の20%近くを占めます。そのエネルギーのほとんどが糖質由来のブドウ糖。
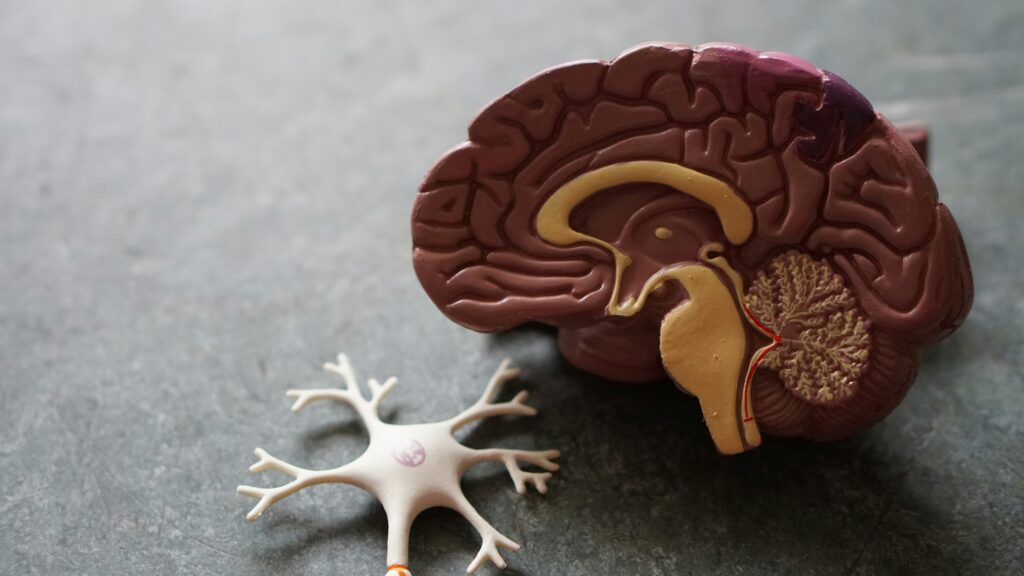
糖質を極端に制限すると、脳がエネルギー不足に陥り、記憶力や判断力の低下が見られることがあります。さらに長期的には、認知症リスクとの関連も指摘されています。特に高齢者の場合、糖質を完全に排除するのではなく、良質な糖質をバランスよく摂取することが大切です。
⸻
1日に必要な糖質のボーダーライン
厚生労働省の食事摂取基準では、総エネルギー摂取量の50〜65%を炭水化物(糖質+食物繊維)から摂るのが望ましいとされています。
例えば、1日2,000kcalを目安にすると…
炭水化物全体:1,000〜1,300kcal
これをグラムに換算すると:約250〜325g(糖質が中心)
ただし、これはあくまで一般的な目安。
ダイエットや糖尿病予防で「糖質制限」を行う場合は、1日 70〜130g程度 に抑える「緩やかな制限」が推奨されることもあります。
それ以下(50g未満)になると「ケトン体」をエネルギー源にするケトジェニック状態となり、合う人・合わない人が出てきます。
まとめると、健康を維持するための 最低限のボーダーラインは70g程度。
ただし活動量や体格によって変わるので、無理のない範囲で調整するのが安心です。
⸻

ご飯200gの糖質はどのくらい?
糖質量を具体的にイメージするには「白ご飯」が分かりやすいでしょう。
白ご飯100g → 約37gの糖質
白ご飯200g → 約74gの糖質
茶碗1杯(150g)だと約55gの糖質です。
つまり、1食で茶碗1杯半食べると、それだけで70g以上の糖質を摂取することになります。
糖質制限中の方は、白米の代わりに玄米や雑穀米を取り入れると、血糖値の上昇を抑えつつ食物繊維やミネラルも補えます。
⸻
適度な糖質制限がベスト
糖質は「取りすぎると肥満や生活習慣病のリスクにつながる」一方で、「取らなすぎると脳や体のエネルギー不足を招く」厄介な栄養素です。大切なのは「質」と「バランス」。

精製された白砂糖や菓子パンは控えめに

野菜・果物・玄米・雑穀を適度に取り入れる
という工夫で、必要なエネルギーを確保しながら無理のない範囲で健康的に過ごしましょう。
我が家では小さい子供がいるので、もち麦ごはんや雑穀米を混ぜたご飯をよく食べています。
⸻
まとめ
糖質を全く取らないことは、疲労感や集中力低下、筋肉減少、さらに脳や認知症リスクにもつながります
ダイエットや健康管理のために糖質を意識することは大切ですが、完全に排除せず「良質な糖質をバランスよく」取り入れることが、体にも脳にもやさしい選択です。
緩やかに糖質制限をする「ロカボ」な食生活を知りたい方はこちらの記事を読んでみてくださいね。記事はコチラ










